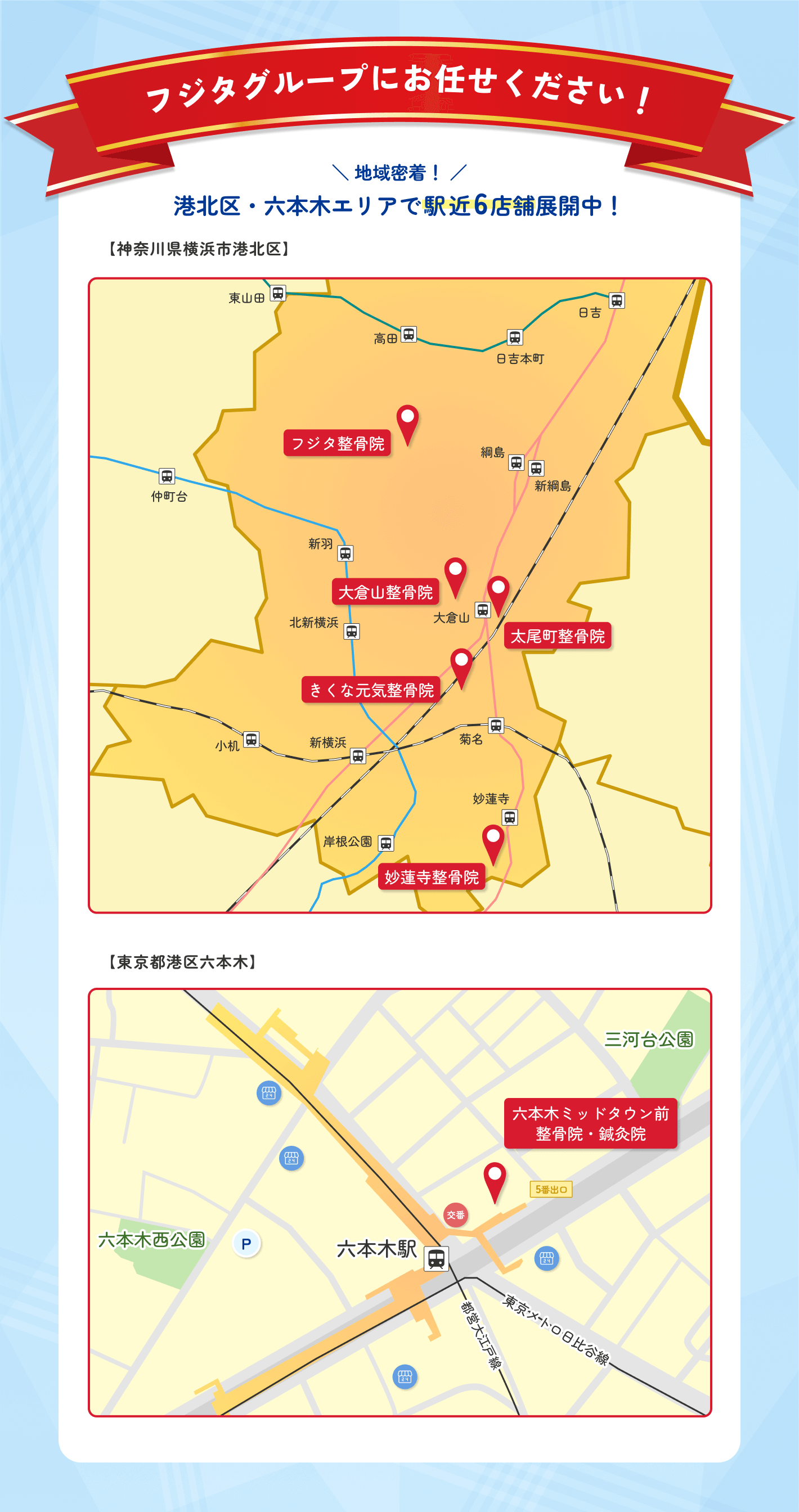交通事故治療について
事故の種類
損保会社のご担当者様へ
【自転車vs車】交通事故の責任と賠償はどうなる?

- 保険会社から治療の打ち切りを告げられた
- 痛みや不調がまだあるのに通院が終わりそう
- 保険会社とのやり取りや手続きが不安
- 交通事故の治療期間はどれくらい通えるの?
- 自分に合った治療期間を知りたい
最近では健康志向やエコ意識の高まりもあって、自転車で通勤・通学する方が増えてきました。その一方で、自転車と車の接触事故も増加傾向にあります。
「自転車は弱者だから、事故が起きれば車側が悪くなるんでしょ?」
「ぶつかったのは車だけど、自転車もちゃんとルールを守ってた?」
実際に事故が起きたとき、責任や賠償はどうなるのか。今回は、自転車と車が関係する交通事故の基本的な知識をお伝えします。
目次
Toggle自転車も“車両”なのでルール違反には責任が問われる
まず大前提として、自転車は「軽車両」の位置づけになっており、道路交通法では車と同様に交通ルールを守る義務があります。つまり、信号無視や一時停止無視、右側通行などの違反をすれば、当然ながら自転車側にも責任が発生します。
例えば以下のようなケースでは、自転車側の過失が問われることも。
- 一時停止の標識を無視して交差点に進入
- 夜間に無灯火で走行
- スマートフォンを操作しながらの「ながら運転」
- ヘッドフォン装着や傘差し運転
上記は全て事故原因として扱われ、自転車が被害者であっても、損害賠償に影響する可能性があるのです。
責任割合は“過失相殺”で決まる
事故が起きた場合、「100%車が悪い」「自転車だから無条件に守られる」ということはありません。事故の責任は「過失割合」によって判断され、双方にどれだけの過失があったかを基に、保険会社同士で話し合いが行われます。
例えば、以下のような状況を考えてみましょう。
【ケース1】
車が一時停止を無視して交差点に進入→直進中の自転車と接触
→車側の過失が大きく、自転車は被害者として扱われやすい。
【ケース2】
自転車が赤信号を無視して交差点に進入→青信号の車と衝突
→自転車側の過失が重くなり、賠償責任も問われる可能性が高い。
このように、状況に応じて責任の重さが変わるため、事故の瞬間を正確に把握することが重要です。できれば事故直後に現場の写真を撮る、防犯カメラやドライブレコーダーの映像を確認するなどの対処が有効です。
自転車側も損害賠償責任を負う可能性がある
意外と知られていないのが、自転車側が「加害者」になってしまうケースです。特に歩行者と衝突してケガをさせた場合など、自転車側が損害賠償を請求されることもあります。
過去には、子どもが乗った自転車が歩行者に衝突し、被害者に約1億円の賠償命令が下った判例もあります。こうした事例を受けて、多くの自治体では「自転車保険の加入義務化」が進んでいるのです。
加害者になってしまった場合、自転車保険や個人賠償責任保険に加入しているかどうかが、金銭的な負担に大きく影響します。特にお子さんが自転車に乗るご家庭は、保険の見直しをしておくことをおすすめします。
被害者になったときの対応ポイント
交通事故の被害者になったとき、大切なのは「早めの対応」です。たとえ軽い接触であっても、あとから首や腰に痛みが出ることはよくあります。事故直後はアドレナリンが出ていて、痛みを感じにくいこともあるため、油断は禁物です。
被害者になった時の対応の流れ
警察に連絡して事故証明を取る
→後日保険を使う場合に必須になります。
医療機関で診察を受ける(できれば当日中)
→レントゲンや診断書の取得は補償手続きに不可欠です。
整骨院に相談して継続的なケアを受ける
→むち打ちや打撲など、レントゲンでは映らない痛みに対処します。
保険会社とやり取りを始める前に、専門家のアドバイスを受ける
→整骨院や法律の専門家から情報提供を受けることで、損をしない対応が可能です。
まとめ:自転車も加害者になることを知っておく
自転車と車の事故は、ちょっとした油断で誰にでも起こり得るものです。そして、事故後の対応次第で、身体の回復も、その後の生活も大きく変わってしまいます。
被害者になっても、加害者になっても、自分と大切な人を守るために
正しい知識と早めの行動が、何よりの“備え”になります。