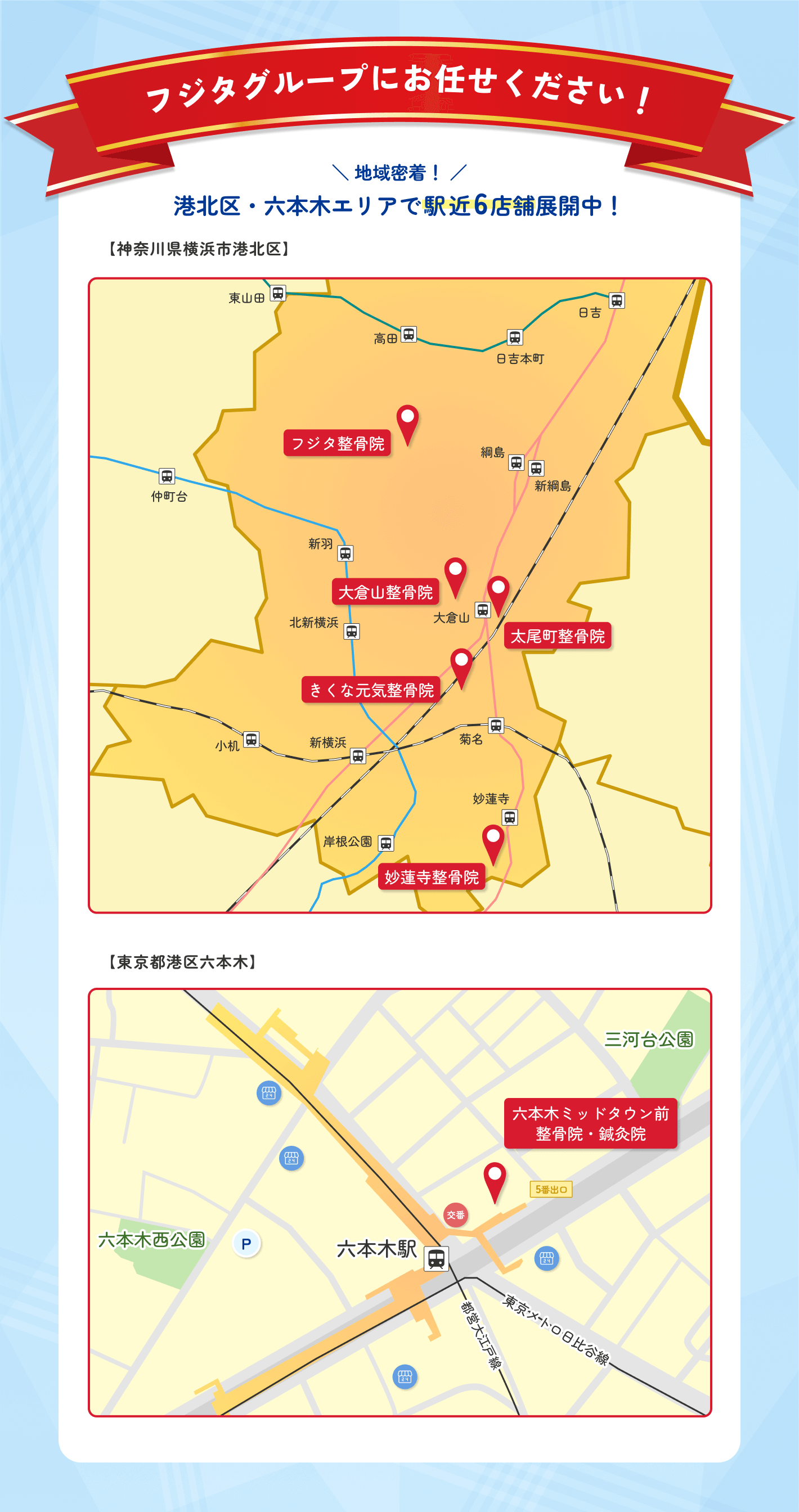交通事故治療について
事故の種類
損保会社のご担当者様へ
意外と知らない?交通事故の損害賠償請求権「時効」が成立する前にやるべきこと

- 保険会社から治療の打ち切りを告げられた
- 痛みや不調がまだあるのに通院が終わりそう
- 保険会社とのやり取りや手続きが不安
- 交通事故の治療期間はどれくらい通えるの?
- 自分に合った治療期間を知りたい
交通事故に遭ったとき、けがの治療や修理の手続きに追われ、損害賠償請求のことはつい後回しにしてしまう方も少なくありません。しかし、損害賠償請求には「時効」があることをご存じでしょうか? 請求できる正当な権利が、知らぬ間に消滅してしまう可能性もあるのです。
この記事では、交通事故の損害賠償請求における時効の基礎知識と、時効が成立する前にやるべきことをわかりやすく解説します。
目次
Toggle時効とは?なぜ損害賠償請求にも時効があるのか
「時効」とは、一定の期間が過ぎると法的な権利を行使できなくなる制度です。交通事故における損害賠償も、法律上の「請求権」であるため、放置したまま一定期間が過ぎると、加害者に対して損害賠償を請求できなくなってしまいます。
これは、時間の経過とともに証拠が散逸し、公平な判断が難しくなるためでもあり、被害者にも「権利を行使する意思」を求める法律の考え方に基づいています。
交通事故における損害賠償の時効期間は?
交通事故の損害賠償請求には、主に以下2つの時効期間が適用されます。
加害者が判明してから「3年以内」
加害者が特定され、損害や後遺障害の程度が明確になった時点から3年以内に損害賠償を請求しないと、原則として時効が成立します。これには以下のような損害が含まれます。
- 人身事故による治療費・慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害に関する損害
- 物損事故による車両修理費など
加害者が不明な場合や悪質なケース:最長「20年」
ひき逃げなどで加害者が特定できていない場合や、損害の発生時期が曖昧なケースでは、事故から20年以内であれば請求可能です。これは民法の「消滅時効の上限」に基づく例外的な扱いとなります。
時効が迫っている場合、どうすれば止められる?
時効は黙っていても進行しますが、一定の手続きを行うことで時効の進行をストップさせることが可能です。代表的なのは以下の方法です。
「内容証明郵便」で請求意思を通知
加害者やその保険会社に対し、内容証明郵便で損害賠償請求を送付することで、時効の進行を一時的に中断する「催告」が可能になります。ただし、催告後6か月以内に裁判や調停を起こさないと、時効は再び進行するため注意が必要です。
訴訟を提起して「時効中断」を確定させる
もっとも確実な方法が、損害賠償請求訴訟の提起です。訴訟が開始されると時効は完全に中断され、判決確定後から新たに10年の時効期間が始まります。示談が進まない場合や、保険会社との交渉が難航している場合は、弁護士に依頼して訴訟に踏み切るのもひとつの選択肢です。
保険会社とのやりとりで注意したいこと
損害賠償請求では、加害者本人ではなく「加害者側の保険会社」とやりとりするのが一般的です。このとき、保険会社が時効成立を主張するケースもあるため、交渉を長引かせない工夫が必要です。
特に、事故から時間が経過しているケースでは「すでに時効ですので対応できません」と断られることもあります。保険会社との交渉に不安がある場合や、示談金の金額に納得がいかない場合は、早めに弁護士へ相談することを強くおすすめします。
時効前にやるべき「5つのこと」
交通事故の損害賠償請求で時効が成立してしまう前に、最低限やっておきたいことを以下にまとめます。
- 事故発生日と加害者特定日を記録する
- 医療記録や診断書を保管し、後遺障害等級が出た日を記録
- 示談交渉の進捗を把握し、停滞していないか確認する
- 必要に応じて内容証明郵便で請求意思を通知する
- 弁護士に相談し、時効の成立を防ぐ法的手段を検討する
時効が成立してしまうと、どれほど正当な請求でも、法的には無効となってしまいます。だからこそ、「まだ大丈夫」と油断せず、早め早めの対応が求められます。
まとめ:時効は「知っているかどうか」で結果が変わる
交通事故における損害賠償請求は、被害者の当然の権利です。しかし、その権利にも期限=時効があるという事実を知らないばかりに、泣き寝入りするケースも後を絶ちません。
「忙しくて手続きが進められなかった」「保険会社との交渉が長引いた」など、事情があっても、法的には「時効だから請求できない」と判断されてしまいます。だからこそ、早めに専門家に相談し、必要な手続きを取っておくことが重要です。